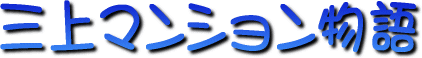
ぽかぽかと、春を先取りしてしまったように暖かい、日曜日。
晴れてよく澄んだ空の青を、窓のガラス越しに浴びる。
そのお日さまのひかりを十分に浴びたフローリングの床にダンボールをことんと置いて、部屋の主は大きくのびをした。
お日さまのような、笑顔。
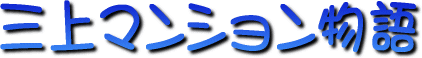
〜 第2話 大騒ぎの、前兆 〜
January 11th, 2001
★ ★ ★
ぱたぱたぱたぱた、朝から大忙し。
荷物をあっちに運んだりこっちに運んだり、ぱたぱた走っては細々した位置を決めていく。
けれどそれは、別に大変な作業ではない。
将自身、それを楽しんでいるからだ。
初見の水野と、仲良くなった。
それが嬉しくて仕方がないのだ。
初めて会った相手と仲良くなることは、実は将にとっては珍しいことでもなんでもない。
だが初めての場所で新しい生活を始めることにほんの少しの不安を抱いていたから、そんな時に声をかけてくれた水野に特別な親近感を抱いたのだ。
不安なときに、ぽんと幸せなことが起きると、そのあとに起こるだろうすべてのことがうまくいくように思えてしまう。
人間なんてそんなものだ。
とはいえ、将はそんな納得はしない。
人と人との関係を計算で括ろうだなんて、将の思考には水素原子ほどもない。
その計算しない純粋さが将の魅力なのかもしれない。
「えぇっと、ティーカップは…そこでしょ。お皿が……」
ボールの模様が描かれたお気に入りの皿が、かちかちと音を立てて並んでいく。
一方、こちら管理人室。
いれたてのコーヒーの香りが漂う。
それは窓辺に立つその人の、左手のカップからたつ湯気と共に部屋中に広がっていた。
三上のその右の手元には、白い書類。
窓枠にもたれかかり、何ごとかを考えながらそれに目を落とす。
真剣な眼差しは、その端正な横顔を映えさせる。
すらりと伸びた脚を軽く組んでたたずむ姿は、やけに絵になっていた。
その三上が、ふいに何かに呼ばれたように顔を上げる。
見上げた先には、何もない白い壁。
そこに、何かを思い浮かべたのか、にや、と笑う。
「……風祭、将」
名を、そっと唇にのせてみる。
不思議な少年だ。
あんなヤツ、見たことがない。
平和なマンションに騒動を起こすのは、管理人の特権だ(と勝手に思っている)。
退屈なのはつまらない。
(せいぜい、楽しませてもらうぜ)
と、そこに。
無機質な音で、電話のベルが三上を呼び立てた。
三上は自分の思考を断ち切られたことにチッと舌を打ち、書類をばさりと放り投げて、足元に転がっていた受話器を手に取る。
「はい、もしもし!」
イラつきをまったく隠さずに通話してきた三上を、電話の向こうで苦笑する気配。
よく知った声だ。
「…なんだ。電話なんぞでなんの用だよ? あ? 仕事してたよ、仕事。オレだって暇じゃねぇんだよ」
電話の相手は、穏やかな声で用件を伝えてくる。
部屋の中には、三上の声だけが聞こえる。
「は? おまえそれ……マジか? 本気で言ってんのか? だってなぁ。…は? オレが? 冗談じゃねぇよ……って聞いてんのかよ」
三上の呆れた口調。
じわじわと、電話料金だけが上がっていく。
ぱんぱん、と膝の埃を払う。
「時間、そろそろ大丈夫かな」
呟いて、将は時計を見遣った。
午後にだいぶ傾いた針。
ああだこうだと配置を迷っていたせいで、片付けはあまり進まなかった。
けれどずいぶんと動いた気がする。
ふぅ、と息をつき、カウンターの上に目をやった。
そこには綺麗な包装紙の、包み。
「よし、行こう!」
言いながら、すっかり作業用になってしまったトレーナーを脱ぐ。
かわりに白いトレーナーと薄手のコートを羽織った。
隣近所への挨拶は、この日本では当然の慣習である。
人情味あふれる下町では、向こう三軒両隣、向かいに斜向かいに町内会に、と果てしなく挨拶回りをしなければならないが、マンションならそれほどではない。
大体両隣に挨拶すればいいものだ。
だから隣の──水野とはもう顔見知りであるから、反対の──家に挨拶に行こう、というのである。
がちゃりと玄関の扉を開けると、さすがに風は少し冷たい。
将はちょっぴり肩をすくめ、すぐ近くにある扉の前に立つ。
歩けば10秒もかからない距離だ。
ピンポーーン。
しーん。
あれ、と将は首を傾げる。
留守だろうか。
もう一度。
ピンポーーン。
すると今度は、扉の奥からはぁい、と気のない返事が聞こえた。
「はぁい。……って、誰やおまえ」
扉を開けたのは、明るい髪の色の(金髪、といってもいいだろうか)少年。
関西弁?
将ははじめまして、と頭を下げると、手に持っていた包みを差し出した。
「えっと、ぼく、303号室に越してきました、風祭将です」
見上げた相手は、きょと、と将を見る。
「あー、隣空き部屋やったから。…しかしまぁ、今時の若いモンにしては律儀なやっちゃのー」
今度は将がきょとんとする。
将は当たり前のことをしているだけだ。
しかし、そのきょとんとした顔が面白かったのだろうか。
突然彼が、ぷっと吹きだした。
「……あ、あの…?」
「す、すまん。おまえがあんま子犬みたいな顔するもんやから、つい、な。…えと、風祭将、やったな」
「はい」
「オレは佐藤成樹っちゅうもんや。シゲ、でええから」
「シゲさん、ですか」
そ、とシゲが笑う。
ほんとはシゲだけでええんやけどな、そう付け足して。
将はそんなシゲの笑顔を見て、
(明るくて、いい人なんだな…)
そう思った。
でも、ほんの少し、違和感?
そんなものが、将の心のどこか片隅をかすめる。
ガチャ。
視線の端で、将の部屋をはさんだ向こうの部屋の扉が開くのが見えた。
あ、と呟いたのは3人ほぼ同時。
どこかへ出かけるところだったのか、コートを着ていた水野がふと目を細める。
「───風祭」
微笑んで名を呼んだ、その響き。
シゲが、わずかに目を瞠(みは)った。
(……へぇ…)
歩み寄ってくる水野に、将もぱぁっと笑顔を輝かせる。
「水野くん!」
(……ほぉ…。このちっこいのも…)
難儀なことになりそうやのー…独白。
しかしそれは顔には出さず、半分開けたドアにもたれるようにして水野の顔をニヤニヤ笑いながら眺める。
「ほーお。タツボンもそんな顔するんやなぁ」
「な…っ、シゲ!」
今頃気付いたように、水野がシゲを睨みつける。
「そォんな怖い顔すんなやー、タツボン♪」
「だからタツボンはやめろって」
そのふたりのやりとりをポケッと見ていた将が、ふいに我に返った。
「シゲさんて、水野くんと友達だったんですか」
言って、すぐにあ、と口を覆う。
「そ、そうですよね。303があいてて、お隣だったんですよね」
シゲは笑って肩をすくめ、
「まぁ、それもあるんちゃうか? そーやな、オレとタツボンはどっちかゆーと…腐れ縁、て感じやないか? のォ」
将は水野を見上げる。
水野は苦笑するふうで頷いた。
「そんなところだろうな」
いいなぁ、と将は思う。
なんだかんだ言いながら、仲が良さそうなふたりだ。
シゲは、将の肩をぽん、と叩いた。
「ま、それはともかく。よろしゅうな、ポチ!」
「え? …ポ、ポチ?」
「もとい、カザ! いや、ホンマ子犬みたいなヤツやからなー」
「シゲ!」
両隣がいい人たちでよかった。
水野とシゲの間で笑いながら、将は冷たいはずの風が気にならないのを感じていた。
(…しっかし、ほんま…難儀なことになりそうやな……)
それは騒動の、予感?
ふたりと別れて、今晩の食事の買物をするために改めて部屋を出た。
夕方にはまだ早い。
けれど、片付けを再開してしまえば買い物に出る余裕もなくなるに違いない。
近くの店にどんなものがあるか覗いてみたいし。
(…あーあ、ぼくって単純なのかも)
将は心の中で呟き、密かに嘆息した。
仲のよい人が増えた。
それが純粋に、嬉しい。
けれど、
(それだけで嬉しいって、変かなぁ)
───それがおまえなんだから。それでいいんじゃないのか。
言ったのは、将の兄、功だ。
(でも、しょうがないよね。本当に、嬉しいんだから)
ことんことんと階段を下りる。
その足取りは軽い。
あっという間に2階に辿り着き、1階へと下りていく。
と、逆に登ってくる長身の影。
ふと視線をあげて。
(あ)
思った。
瞬間、脳裏にフラッシュバックする、夕暮れの景色。
向こうも顔を上げる。
視線があう。
呆然と見つめる将の目の前で、その人が笑った。
「風祭くん? だったよな」
(え…? し、渋沢さん)
渋沢は階段を登る。
将の立つその数段下で立ち止まって。
「あ…っ、あの…。ぼくのこと……憶えて…」
「あぁ、やっぱりそうか。引っ越しの荷物を運んでいるのを見て、もしやと思ったんだ。久しぶりだな」
「はっ、はい!」
将はこみあげてくるものを感じた。
何年か前のこと。
同じ学校の、憧れの先輩だった。
いつも大勢の人たちに慕われ、その人の輪を羨望のまなざしで見ていたのだ。
渋沢にとって、将は知るはずもない存在だったから。
それでもただ一度だけ、サッカーの練習に付き合ってもらったことがある。
家の都合で転校する、直前だ。
夕暮れのグラウンド、ふたりだけの。
「もしかして、買物か?」
「あ…はい」
「よかったら、うちで夕飯を食べていかないか」
「えっ!?」
突然の申し出に、思わず将は驚きの声をあげる。
けれど渋沢は動じない。
穏やかに微笑んで、
「せっかく久しぶりの再会を果たしたんだ。それに引っ越しの片付けで夕飯の仕度をするのは大変だろう? ささやかだが、歓迎会を開かせてくれないか」
そう言われてしまうと。
どうも断れない。
いや、実を言えば、とても嬉しいのだけれど。
(渋沢先輩が、ぼくを歓迎してくれるなんて)
でも、それは渋沢に負担をかけることになるし。
だから、
「…渋沢先輩が、かまわないとおっしゃるなら」
と答えるにとどめた。
対して渋沢は笑顔だ。
「もちろん。俺が誘ったんだからな」
あとでちゃんと、手伝いに行きますから。
そう言った将の、階段を登っていく背中をとても暖かい思いで見送る。
昔から、なんにでも一生懸命な子だった。
周りの子供たちが目立とうと必死になっている裏で、ひとり努力を続けているような子だった。
笑顔が、眩しい太陽のようで。
渋沢は、そのころからちゃんと将のことを知っていたのだ。
人知れず努力する将を、時には暖かく、時には心配しながら見ていた。
最初から、ずっと気になっていたのだ。
ここにも、ひとり(笑)。
そこに、階下から騒がしい声が聞こえた。
「あー。キャっプテーンっ!! 何やってるんスか、そんなとこで!」
ふと視線を落とすと、スポーツ系らしい、さっぱりした髪の少年がコンビニエンスストアの袋をぶんぶんと振り回して笑っている。
その後ろには、器用にその袋をよけながら渋沢に会釈をする猫目の少年。
「藤代、笠井。……いたのか」
「やだなぁ、キャプテン。ちょっと前からいましたって」
藤代の持つ袋には、スナック菓子がわんさか入っている。
渋沢はそれに目をとめて、わずかに顔をしかめた。
「…また買ってきたのか? 健康上よくないと、前から言ってるだろう」
「えー。ちょっとだけですよ、ちょっと」
「そのちょっと、が積み重なればすごい量になるんだぞ」
負けそうになった藤代は、ちらりと後ろの笠井を見る。
笠井は仕方ないな、というように息をついた。
「…それよりキャプテン。今話していたあいつ…誰ですか」
急に話を差し替えた笠井に、渋沢もそれが藤代に対する助け船だと気付いたのだろう。
少しばかり苦い笑いを浮かべ、
「古い知り合いだ。昨日ここに越してきたばかりでな。だから今夜は、あいつの歓迎会を開こうと思っていたところだ」
そう言うと。
とたんに藤代の瞳が輝いた。
「パーティ!? パーティやるんですかっ!? ……キャプテーン…v」
両手を組んで、お願いのポーズ。
渋沢は今度こそ、苦笑した。
「最初から、おまえたちには声をかけるつもりでいたよ」
「それで、キャプテン。他に誰か呼んだんですか」
「あぁ。風祭が友人を連れてくると思うが」
「他には?」
「あと三上には声をかけた。それだけだな」
「三上先輩に? へーえ、先輩文句言ってたでしょ」
「よくわかったな、藤代」
「えー、だって三上先輩ってわかりやすいとこあるじゃないですか」
───くしゃんっ。
ひとつクシャミをして、三上は憎々しげに天井越しの階上を睨む。
「…ぁーた誰かオレの噂話してやがるな……」
将の歓迎パーティは、はてさて一体どうなるやら?
continued ♪
| <After Words> |
| お待たせしました(ほんとにな)!! 三上マンション物語、第2話でございます。 もお、パロディもパロディなもので、そろそろ早くも無理な設定が飛びだして参りましたね。 まずは呼称。なんて呼ばせればいいのやら。 それから、過去。とりあえず渋沢には会っとかないとアレだよなぁ……。 そんな時には妹。(仮)先生にご相談です。妹。(仮)さんは、時たまマニアックな設定もなさいます。 それもすべて「ギャグパロディだからいいんだもん」コレでおしまい。 便利な言葉だなー。 さてさて、渋沢がなんだか一個駒を進めた感じですね。とりあえずは。 藤はともかく、笠井っち出しちゃったよ…なぁ…(いろいろな意味でとりあえず遠い目)。 それから、シゲさんなぁ。大好きなんだけど…。鬼門だ……関西弁。わかんないんですよーーー!! あー。次回は、今回ほどお待たせしないといいなv なんて思ってますv てへ。 |